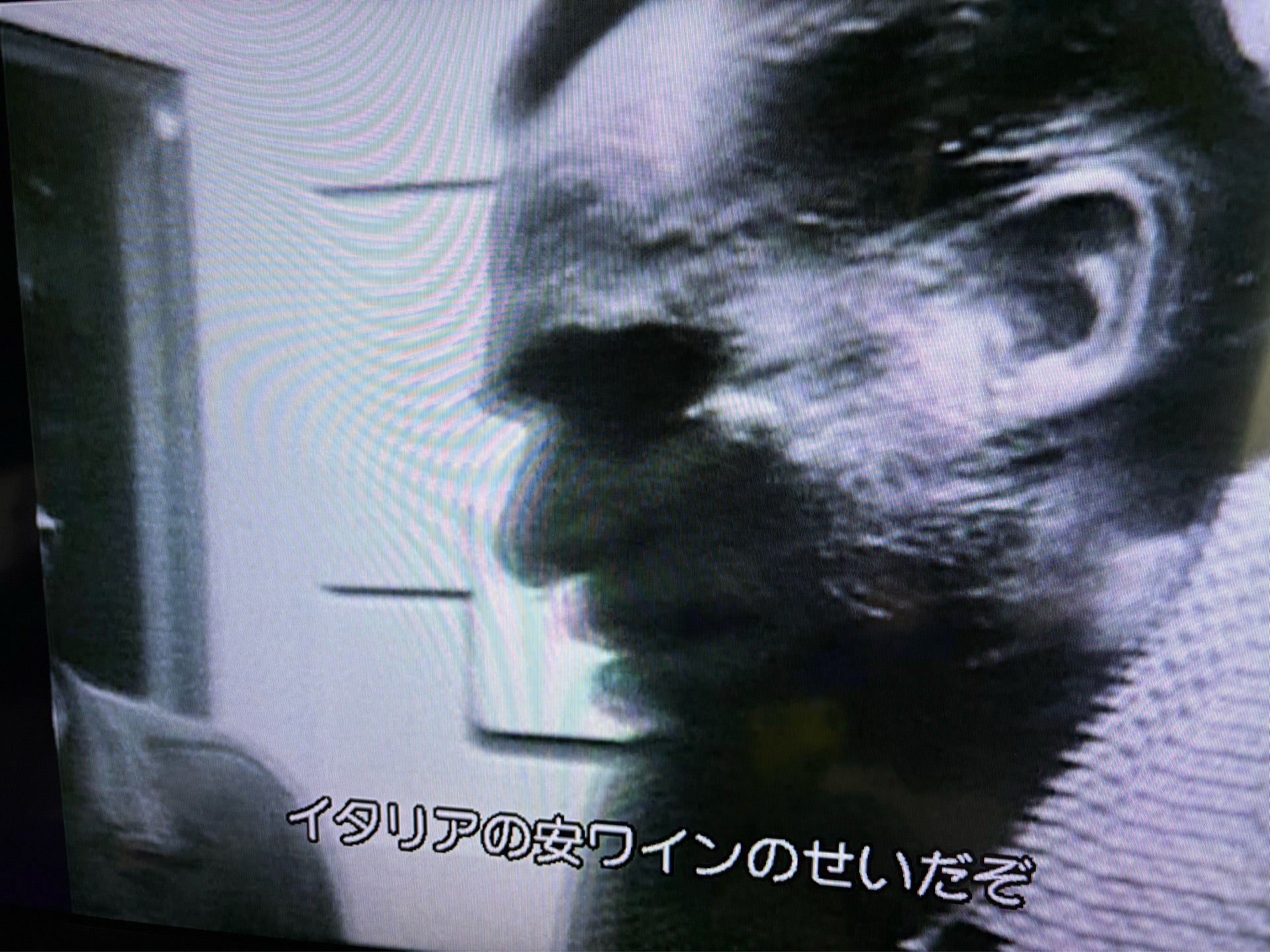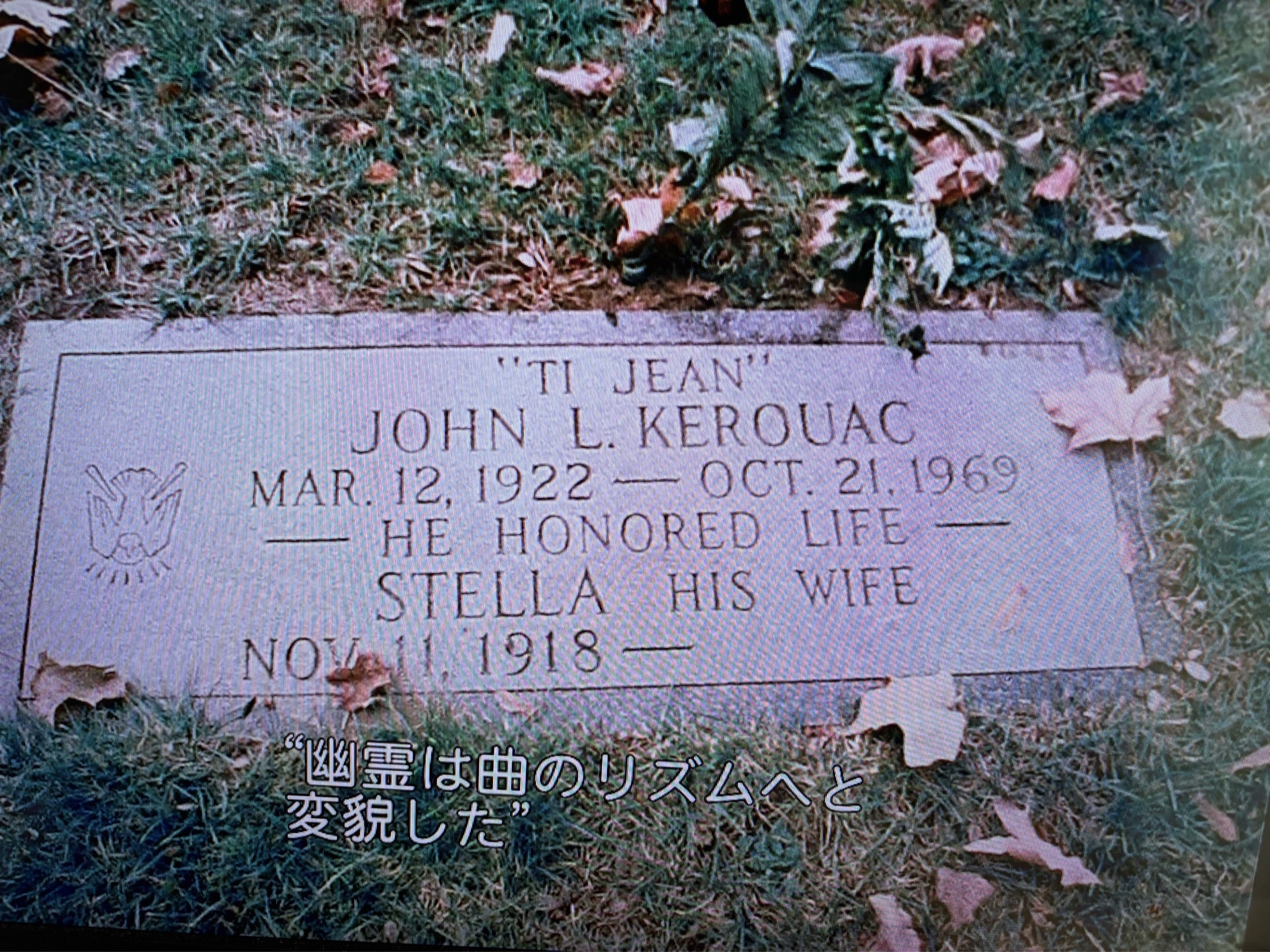No fun
トーク情報- No fun
No fun ![投稿画像]()
最近では一つのジャンル化した感のある同性愛モノ。
バロウズ原作ということもあり『クィア』を観に行きましたが、恋愛モノいうよりバッドトリップを擬似体験する作りになっていました。
原作のドライな文章がそのまま視覚化された様な一部と、気怠さと切なさがズシンと響く二部、ジャングルを舞台にしたホラー仕立ての三部の構成。
奇妙(クィア)に歪んだ「6代目ボンド」ダニエル・クレイグの演技は、常に死と隣り合わせのジャンキーの生態がリアルに表現されていて、器の大きさを感じる事が出来た。
「ウィリアムテルごっこ」など原作にない逸話も幾つか出て来る。
これは、バロウズ本人に興味を持って欲しいという監督や脚本家の意図もあった様に思う。
確かにメキシコ逃亡期の実話で、時代背景もマッチしているが、本作をイカれたおじさんの悔恨話と観る人もいそうで少々残念。
ハーバードを卒業するも、定職につかず親の遺産で食い繋ぐ、所謂穀潰しの毎日をニューヨークで送っていたが、既にドラッグ中毒になっていたバロウズ。
確かにダメ人間ではあるが、『クィア』は中毒から抜けた頃に書かれたもの。
ダニエル・クレイグが良かっただけに、原作に忠実に、辛く切ない物語に仕上げて欲しかった。 - No fun
No fun ![投稿画像]()
ケルアックの墓前で詩を朗読したり、ギンズバーグへの膨大なインタビュー映像から、文学、主にビートニクが与えた影響を可視化出来る『ローリング・サンダー・レヴュー:マーティン・スコセッシが描くボブ・ディラン伝説』
ディランへのインタビューも当時を振り返る内容のものばかりなんですが、終始けむに巻く様な話し方で、いつも通り(?)インタビュアーの質問にも適当な返答をする場面が多い。
中でもギンズバーグが歌唱するシーンが出て来るが、彼の歌について聞かれても「彼は素晴らしいダンサーだ」って。
答えになってない。
そうそう、これですよ、これ。
こういう本物のディランを観たかった。
実際のギンズバーグの歌声はソフトで、楽器の演奏もかなり上手い。
詩で成功した後は音楽をやりたかったそうですが、それも納得出来るほどのクオリティなのに、ディランはダンスを褒めてばかりで、観ている自分も何が何やらわからなくなる。
しかもシリアスな表情で声のトーンも低めだから尚更です。
トリックスター的な顔と、新しいものを常に吸収しロックに文学と社会性をサラッと取り入れた先駆者的な顔。
どこまでが実像でどこまでが虚像か分からない、ボーダーレスなスタンスに憧れます。
「文は人なり」って言葉はコンプリートアンノウンには通用しない。 - No fun
No fun ![投稿画像]()
不思議な紀行文でした。
遺作と知っていたので総括的な内容なのかと構えて読んだけれど、読み易くて面白かった。
街の景色やそこに生きる人々に対する鋭い視点は健在だが、浮かない感情が全体を包んでいる為、結論に至らないまま書く事を放棄しているような印象を受けた。
更には藤本和子さんの軽やかな言葉が本書全体の寂寥感を強める効果となっています。
複雑な感情は単純化され、誇張やユーモアに対する危惧も感じられる文体は、読み進めるほどに心地良い。
これは、ブローティガンの中にあった(であろう)、表現における一種の羞恥心のせいだろう。
それと、仏教や東洋哲学の暗喩表現が多い気はしたが、日本人ならスッと腹落ちすると思う。
書いた人しか分からない感覚に触れる事が読書の楽しみだし、血肉化されている言葉だからこそかも知れないけれど。
全てのエピソードが現実に起こった事だとは思わないが、不運な女性達に思いをはせているうちに、最終的に死への渇望に繋がったのかも知れない。
カッコよく言えば、他人の人生を通して、自分の人生の到達点を見つけたって感じですね。
今年読んだ本の中では現時点でトップ。 - No fun
No fun ![投稿画像]()
「きょうの特製はミート・ローフだろう」とエドワーズ先生がいった。
「そう。灰色の日にはミート・ローフが一番。それがあたしたちのモットー!」と彼女は答えた。
みんな笑った。おかしかったもの。
(Rブローティガン『西瓜糖の日々』 河出文庫)
「きょうは挽肉向きの日だと思うけどねぇ。外を見てごらんよ。曇ってる。雲の中には雨が入ってるんだ。あっしなら挽肉にするね」と彼がいった。
「やめとく」と彼女はいった。
(Rブローティガン 「サン・フランシスコの天気」『芝生の復讐』 新潮文庫)
ブローティガンの小説に関する感想は中々書けない。
語彙力とかそういう問題でもない。
さっぱりわからないからだ。
けれど、現実でも絶対にあり得ない会話でもない。
だから何度も読んでしまう。
昔、早逝した編集者が「私は物語を守る者でありたい」と語っていたが、正しくそういう作品だと思うし、守る、イコール安易に触れない事だと思う。
人生について知るべきことは、すべてフョードル・ドフトエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の中にある、と彼はいうのだった。
そしてこうつけ加えた、「だけどもう、それだけじゃ足りないんだ」
(カート・ヴォネガット・ジュニア『スローター・ハウス5』 ハヤカワ文庫)
ブローティガンもそうだが、「足りないもの」を補ってくれるであろう作品はあるにはあるが、絶版のものが多い。
サブスクの映画も同じ事が言えるけれど、何とかならないものかなぁ。
本当の意味で物語を守って欲しいものだ。 - No fun
No fun ![投稿画像]()
19歳から21歳まで、某大手レンタルチェーンでバイトしていました。
その店のルールというか特典に、新作以外の洋画は何本持ち帰ってもOKというシステムがあり、映画を観るという事に相当時間を費やしていた貧乏学生には有難かったです。
最初は手当たり次第に観ていたけれど、洋画コーナーの責任者になってからはPOPを書いたり、リコメンドコーナーを作るために半ば仕事の為に観ていた気がするが、それでも充実した楽しい日々を過ごせていました。
その頃に観た中で印象的だった2作品を、最近サブスクで見つけました。
フリッツ・ラングの『M』は、ナチスが上映禁止にしたいわく付きだけれど、現代にも十分通じる普遍的恐怖が主題。
ジャン・ルノワールの『ピクニック』は、ジョルジュ・バタイユ本人が出演しているなど、資料としても貴重な作品。
どちらも辛うじて戦禍を生き延びた映画でもあります。
前回「物語を守る者」という言葉を使ってサブスクのチョイスを批判したけれど、今回は素直を謝ります。
欲を言えばベルイマンの作品と、70年代アメリカ映画をもう少し配信してくれればいいんだけどなぁ。
まぁ気長に待ちます。