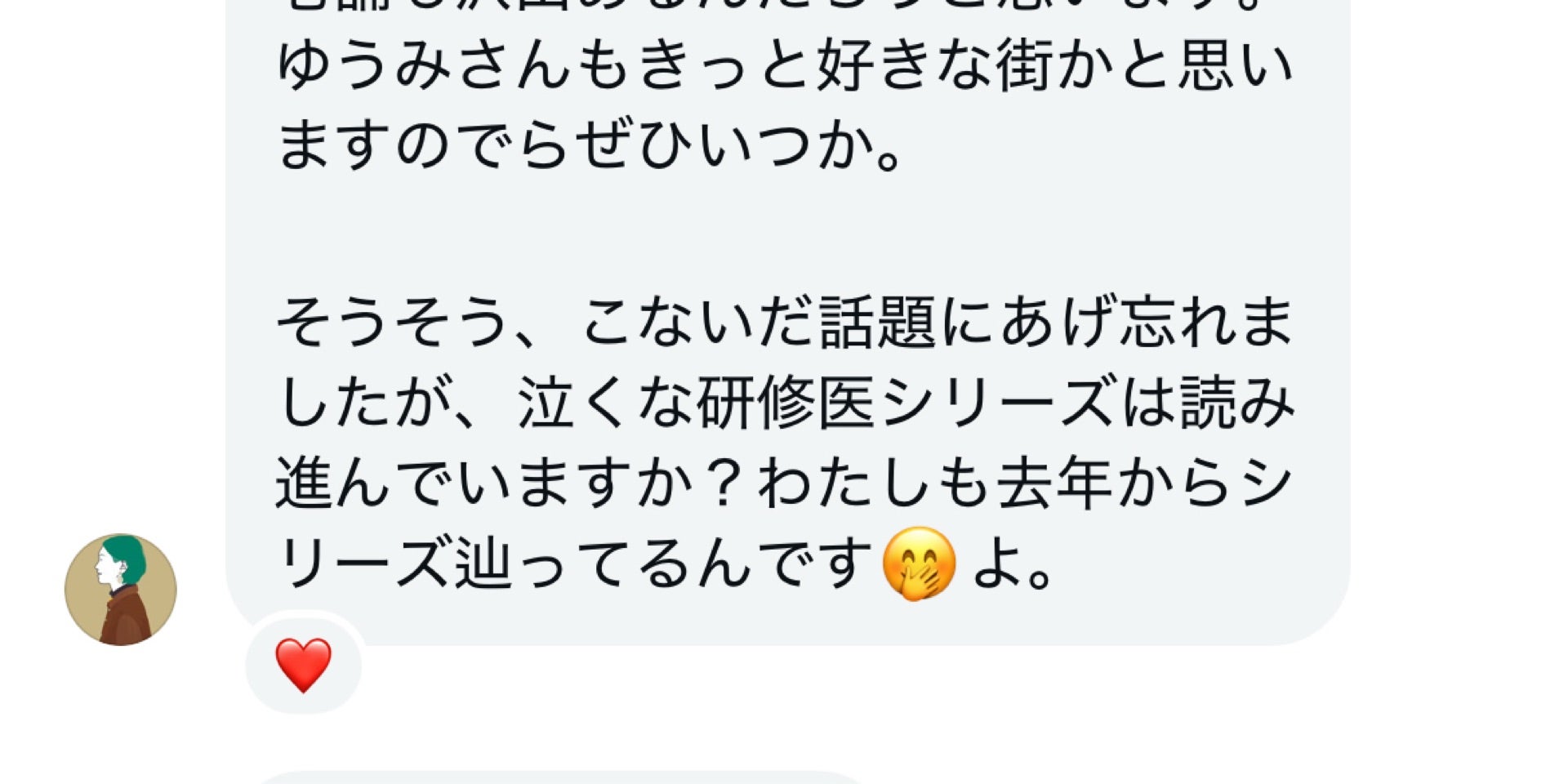umiのトーク
トーク情報- umi
umi ![投稿画像]()
電車のなかで読む予定だった[逃げるな 新人外科医]。時間の都合で車になりオーディブルで聴くことに。主体的なテンポで読むとは違った疾走感が並行世界(いま)に新人外科医の雨野先生が存在しているかのようで、それも読むとは違う良さがありました。
恋も、仕事も、片隅のひと(患者さん)も、お父さまも、喜びも、悩みも、悲しみも、生も、死もーー全て同じ質量で自他に向かい、事に当たる雨野先生の誠実さゆえの四苦八苦が初冬の西陽同様にわたしには煌めいて映りました。
先輩医師佐藤に確認せずに進めてしまったことで患者さんの肺を傷つけてしまったことからも、患者さんや父の死からも、恋からも逃げない。作業に陥らず、不感症にならず、一つひとつ感じ切る。
その態度が雨野先生の医師として、そして人間としての理想と現実の差分を少しずつ埋めて"いい医者"(他者にとってはすでにそう映っても、雨野先生にとっての)に近づいていっているように感じました。
アメちゃんの恋の行方、佐藤先生や岩井先生の素顔、んー、続きが気になります。
そして、本でももう一度読もうと思いました。 umi 藪 医師(中山祐次郎)藪 医師(中山祐次郎) umiさん、素敵なご感想ありがとうございます。オーディブルだとまた違う印象を受けますよね。
初冬の西陽。言い得て妙ですね…。この先も彼をたくさんの試練が待ち受けています。お読みいただき、ありがとうございます!